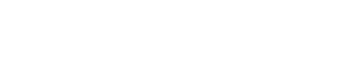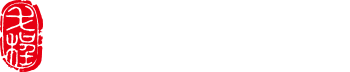【案件による法の解釈】「最も近い先行技術の誤った選択」は、必然的に進歩性の評価に影響を与えるのでしょうか?
2025-04-28
案件の簡単な紹介
かかる特許の名称は「傾斜ノズル付きポンプディスペンサー」、出願日は2012年10月25日、優先日は2011年10月25日、特許出願人はA社である。実体審査の後、国家知的財産局(以下、CNIPAと称す)の元の審査部門は、出願が特許法第22条第3項に規定された進歩性を有しないという理由で拒絶決定を下した。A社は拒絶決定を受け入れることを拒否し、CNIPAに覆審請求した。そして、CNIPAは拒絶査定を維持するという決定を下した。
A社は被訴決定を受け入れることを拒否し、北京知的財産裁判所に訴訟を提起した。主な理由は下記のとおりとなる:請求項1と引例1とは、それぞれの技術課題、技的効果、および用途が類似しておらず、両者の間には多くの区別技術特徴がある。したがって、引例1は最も近い先行技術に適格していない。したがって、裁判所が被訴決定を取り消し、新たな決定を下すよう請求した。北京知的財産裁判所は、2021年5月26日に判決を下した。
裁判官の解釈
実際には、異なる既存技術から発明創造に至るまでにいくつかの経路があり、各経路は、当業者にとって難易度が異なる。「特許審査ガイドライン」では
多くの既存技術の中で、「最も近い」既存技術、すなわち「すべての既存技術の中でクレームされた発明に最も密接に関連する技術的解決策」を、自明性判断の出発点とする基本的な理由は、すべての既存技術に対して進歩性のある発明のみが特許化することを保証するためである。そして、最も近い既存技術と比較して進歩性ある技術的解決策であって初めて、すべての既存技術全体に対し技術的貢献ある発明になる。
したがって、ある技術的解決策が1つの既存技術に対し進歩性あるが、別の先行技術に対し進歩性ない場合、後者は前者よりも技術的解決策の進歩性を評価するための「最も近い既存技術」として適している。
「特許審査のガイドライン」は、最も近い既存技術を確定する方法を例示する:
「クレームされた発明の技術分野、解決しようとする技術的問題、技術的効果または用途と最も近い、および/または発明の最も多い技術的な特徴を開示した既存技術;クレームされた発明の技術分野とは異なるが、本発明の機能を実現し、本発明の最も多い技術的な特徴を開示した先行技術」。上記の条件を満たす既存技術は、通常、クレームされた発明に最も近い既存技術であるので、「特許審査ガイドライン」は、それに応じて審査官および無効宣告請求人にガイドラインを提供したが、最も近い既存技術が必ず上記の条件を満たすわけではない。
本案の場合、原告が引例1を最も近い既存技術と見なすべきではないと主張する理由は、本発明が進歩性を具備することを証明するためである。しかし、前述の理由に基づき、引例1を出発点として「三段階法」により本発明が進歩性なしという結論まで至るなら、被訴決定における進歩性に関する結論は正しい。引例1がすべての既存技術の中で「最も密接に関連する」ものであるかどうかに関しては、進歩性判断の焦点でもなく、訴訟の結論を覆すのに十分でもない。したがって、原告の主張が支持できない。
北京知的裁判所
2022年3月10日